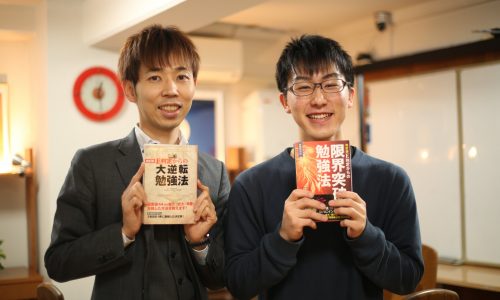なぜ宗教に対して否定的なイメージをもってしまうのか
神道家 羽賀ヒカルです。
日本人の心には、数多くの宗教が息づいています。
ほぼ全ての人が、「いただきます」と手を合わせ、クリスマスを祝い、神社に初詣に行き、仏壇に手を合わせる。
ほとんど意識しないくらい、色々な宗教が暮らしに溶け込んでいるのです。
それにも関わらず、「宗教」という言葉にアレルギー反応を示し、なぜか「近付きたくない」というネガティブなイメージを抱いてしまう現代人が多いのです。
なぜでしょうか?
ニュースになる凶悪事件(オウム真理教、イスラム教過激派など)をマスコミが煽り、「宗教=マインドコントロール・洗脳」というイメージが刷り込まれたことが大きな要因でしょう。
また、胡散臭い新興宗教の勧誘から、ネガティブな印象を持った方も多いかもしれません。
そして最大の理由は、その人自身が宗教に対して正しい知識を十分にもっていないことでしょう。
その証拠に、信仰を否定する人たちは、たいてい「神道の起源は?」、「天皇ってどういう存在?」などの初歩的な質問にも答えられません。
無知であるがゆえに世間の論調に合わせて「なんか怪しいよね…」としか言えない状況がうまれてしまうのです。
例えば、私の師匠である北極老人が、大学受験塾ミスターステップアップの塾長をされていたとき。
寝る間を惜しんで塾生の親御さんや近所の方の人生相談にのられたり、食生活が乱れている子のために、ただただ塾生の幸せを願い手料理を振る舞ってあげたりしていました。
誰かの幸せのためなら、どんな苦労もいとわない方だったのです。
そこには100%の善意しかありませんでした。
ところが、無償で何かを施すような塾はなかなかお目にかからないものですから、心ない人たちから、「あの塾って宗教なの?」と怪しまれることも多かったそうです。
つまり、無償の愛で生きると怪しまれる世の中なのです。これって、すごく嘆かわしいし、由々しき問題だと思いませんか?
「無宗教」ではなく「多宗教」なのが日本人

日本人は「無宗教」だと主張する人がいますが、正しくは「多宗教」です。
本当の「無宗教」とは、神を信仰しない主義のこと。
これは海外では常識ですが、日本では理解している人が少ないのです。
日本人は、もともと日常生活を通して、神様への感謝と祈りを形にしてきた民族です。
古来より日本に伝わる古神道には、数ある宗教を調和するような考え方がつまっています。
異質なものを排除したり、この教えだけが正しいと自己主張したりということは古神道の精神にはありません。
あらゆる宗教を万遍なく取り入れてこられたのは、そこで寛容な精神が育まれていたから。
そんな国は世界中を見渡しても日本しかありません。
日本ほど、多神教が豊かに花開き、一神教も取り入れ和合している国は他にないのです。
これって、本当に凄いことなんですよ。
神の如き武将がいた

時代の覇権を握った天下人や、かつての名武将には、ある共通点があります。
それは、ほぼ例外なく、篤い信仰心をもっていたこと。
武将・武田信玄は諏訪大社を崇拝し、戦の前には必ず戦勝祈願をし「戦は魔法にて候」と言うくらい、神を頼りにしていました。
対する上杉謙信は毘沙門天を信仰していたことで有名です。
軍神と呼ばれるほどの圧倒的な強さを誇り、毘沙門天の化身だと恐れられたほど。
謙信公は15歳で初陣を果たしてから49年の生涯を終えるまで、ほぼ百戦百勝。
まさに〝神がかり的〟な勝率を残しているのです。
戦場は生きるか死ぬか。
武将の瞬時の判断に、何千、何万の命が委ねられる。
その想像を絶するような重圧の中で、自分が死ぬことの恐怖に怯えていては、判断が狂います。
それ故、将たるもの、命がけで守るべき信念がなければ、軍を率いることはできないのです。
謙信公は、戦況に応じて即断即決の行動をとり、まるで兵を手足のように動かした。
そう言い伝えられています。〝一人間〟の視点ではなく、まるで上空から見下ろすように、民を守り、国を守る、神の如き視点から、この世を眺めていたからこそ、そのような神業を為し得たのでしょう。
戦後日本が復興できた理由

近世では、ビジネスは戦に例えられます。
揺るぎない信念が求められるのは、武将のみならず、経営者も同じ。
たった一つでも経営判断を誤れば、多くの社員と、その家族を路頭に迷わせるかもしれないのですから。
日本の高度経済成長を支えた大経営者、財界人の活躍を裏で支えたのも、並々ならぬ信仰心でした。
「経営の神様」と称される松下幸之助は、数々の宗教宗派を深く学んだといいます。
今もパナソニックの社内には守護神を祀る神社があり、その経営哲学は〝松下教〟とも呼ばれました。
『海賊とよばれた男』の映画や小説のモデルとして話題となった出光佐三(出光興産創業者)も信仰の篤い人物でした。
石油事業で日本の復興に尽力して成功を収めた後、地元・福岡県の荒れ果てた宗像大社を復興したのです。
投じた私財は数十億円に及び、約30年を費やしたそうです。
大手電機メーカーの「Canon」の社名も、観音様の御慈悲にあやかり世界で最高のカメラを創る夢を実現したい、との願いを込めて付けられたといいます。
このような例は数え上げればキリがありません。
誰もが名前を知る大企業の数々は、神々への信仰に支えられていた。
これは、神様の存在を信じようが、信じまいが、偽りのない事実なのです。
今、私たちは当然のように便利な暮らしの恩恵を受けていますが、戦後の焼け野原から現在に至るまで、先人たちの途方もない努力がもたらした奇跡だということを忘れてはならないでしょう。
そして敗戦を乗り越え、「私のため」よりも「国のため」、「みんなのため」に働き、奉仕し続けた姿こそ、日本人の信仰心の賜物なのです。
損得を超えて、誰かの幸せを自らの喜びとし、生きがいとする。人がその美しい生き様に目覚めるとき、本物の信仰心がそこにあるのです。
日本を骨抜きにした戦後教育

「宗教」という言葉に否定的なイメージを持ってしまう方も、病に伏した家族の無事を祈ったり、大切な誰かを亡くしたあとも、なんとなく近くにいるように感じたり…。
そのとき、目に見えぬ何かに畏敬の念を抱き、手を合わせたことがあるのではないでしょうか。
そういった感覚こそ、日本人がナチュラルにもつ信仰の種です。
信仰の芽生えとは、特定の宗教団体に入ることではなく、悔いのない人生、誇らしい人生、幸せな人生を全うするために、限られた命を〝何のために〟使うか。
その腹を決めて生きることなのです。
本物の信仰心には、凄い力が秘められています。
戦前の日本は、こんな小さな島国でありながら、戦争をすれば欧米列強を脅かす存在でした。
国民性も世界が認めるほど素晴らしかった。
それが、諸外国にとって脅威だったのです。
そのため、戦後GHQは日本人を骨抜きにする政策をとりました。
この時に、「宗教=悪いもの」という思考が吹き込まれたという歴史的背景があります。
今、学校やマスコミが教える歴史は、日本をまるで悪者のように教えています。
けれど真実の歴史を学ぶほど、日本には世界に誇れる歴史があります。
そして何より、今現在の世界を眺めても、一流の人物の多くが、日本を称賛し、その精神性に憧れているのです。
日本人なのに、日本のことを語れない。それは誠に不甲斐ないことでしょう。
日本は〝和〟の国です。あらゆる思想や宗教をうまく取り入れて、良さを引き出し、調和させるのが良さなのです。
まず日常の中で、他人と考え方の違いでぶつかりそうになったら、調和できる点を見つけてみてください。
そして、その良さを発揮するためにも、まずは自国のことを学んでいきましょう。