良縁を繋ぐお茶屋「茶肆ゆにわ」店長こがみのりが語る茶話。
今回は「香り」についてのお話です。
「方向付け」=「芳香付け」

©『神様に愛される一杯のお茶習慣』(自由国民社)撮影:竹田俊吾
お茶の「美味しい」「美味しくない」は、香りの違いによるところが大きいんです。
では、お茶を淹れるとき、どうすれば、良い香りを引き出せるのでしょうか。
そのためには、ちゃんと「方向付け」してあげることです。
「方向付け」=「芳香付け」です。
方向付けできない時は、自分の中に迷いがある証拠。
では、なぜ迷うのかといえば、理由は単純。
その茶葉のことをちゃんと知らないからです。
まず茶葉のままの香りをよく嗅いでみる。
そして、それがお茶になって香りが広がったゴールをイメージする。
このイメージがなければ、苦みや渋みが出過ぎないように、と考えすぎて弱気になりがち。
すると、香りも弱々しくなってしまいます。
以前、なかなかお茶の香りが出せないと悩んでいた方が、その茶葉の産地の写真を見てイメージを膨らませて淹れるだけで、一気に美味しくなったことがありました。
茶肆ゆにわの香り

お茶の香りを感じたら、それに合うお香を探してみるのもいいでしょう。
茶肆ゆにわでは、毎日お香を焚いています。
お客様によく、「家でも茶肆の香りを再現したいので、使っているお香を教えてください」と聞かれますが、答えはその度に変わります。
お茶に合う香りを選んで焚きますので、決まった答えがあるわけではないのです。
さらに、「同じお香を揃えただけでは、茶肆と同じ香りにはなりませんよ」と付け加えます。
なぜなら香りとは、極めて重層的なものだからです。
例えば、茶肆の香りを作る要素が100あるとします。
茶葉を焙じる香り、茶釜の沸き立つ香り、土壁の香り、柱や机の古木の香り、畳の香り……、数え上げればきりがないほど、様々な香りが折り重なって、茶肆ゆにわの香りができているのです。
お香は、100あるうちの、たった1要素でしかありません。
1要素を同じにしても、残りの99が違っていれば、まったく別の香りになります。
ですから、同じ香りを目指すことよりも、それぞれの場の役割や特性に合わせて、お香を上手に使うことが大切でしょう。
お香の役割は、その空間に99の香りが漂っているとしたら、最後の「1厘」を加えること。
それによって香りは「方向付け」されて、一つにまとまるのです。
香りは〝気〟の乗り物

「方向付け」とは何でしょうか?
そのお香を使う目的をはっきりさせることです。
- 空間を浄化したい。
- 芳しい香りでお出迎えしたい。
- 印象的な香りでお見送りしたい。
- リラックスしてほしい。
- 気分を盛り上げたい。
- 大切なメッセージを伝えたい。
そういった目的意識をもつ。
すると、その局面に応じて、最も適したお香の種類や、焚くタイミングも自ずとわかるようになります。
そして不思議なことに、どんな〝気持ち〟を乗せるかによって、同じお香でも、香りは明らかに変わります。
香りは、〝気〟の乗り物なのです。
古来から、あらゆる宗教においても、儀式の際には香りが多用されてきました。
お仏壇で線香を焚くのは、邪気邪霊を寄せ付けないため。
ご先祖様と気持ちを通わせるためです。
キリスト教でも意識覚醒のため香油が使われました。
古神道の神事では、神様を降ろすために大麻草が焚かれていたそうです。
私もここぞという時は、神社の神様の〝神気〟をお迎えするような気持ちで、お香を焚きます。
すると、まるで時空を超えたかのように、茶肆にいながらにして、神社の空気が再現されることがあるのです。
自分の意識を方向付けすることで、香りを操り、空気をつくる。
それがお香の活用法なのです。
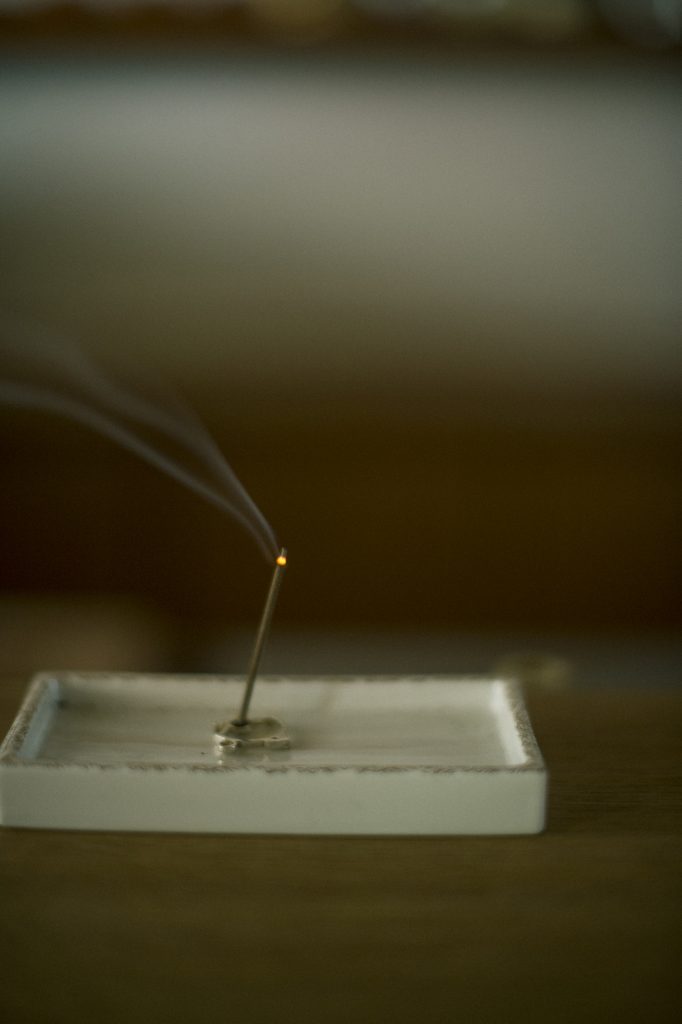
©『神様に愛される一杯のお茶習慣』(自由国民社)撮影:竹田俊吾
香りを使う前に注意したいこと
香りを使う前に、注意すべきことがあります。
それは良い香りを加えようとする前に、まず嫌な臭いをできる限りゼロにしておくことです。
そのためには、事あるごとに換気をするクセをつけましょう。
空気が停滞すると邪気が発生します。
邪気の多い空間は必ず臭くなるのです。
「部屋が臭いから、良い香りのお香やアロマを焚こう」という発想をする人が多いのですが、それは逆効果。
香りに香りを上乗せすると、雑多な気が混ざって、かえって臭くなってしまいますから。
私が場を浄化するためにお香を焚くときは、香りの少ないお香を選びます。
そして、モクモクと空間いっぱいにお香の煙を広げます。
その後、換気をして煙を外に流す。
煙に邪気を乗せて、一気に追い出してしまうようなイメージです。
空間に、なんとなく嫌な臭い、悪い気が残っていると感じた時には、ぜひ試してみてください。
抜群の効果がありますから。
あとは一にも二にも掃除です。
掃除は水拭きが基本。
臭いが染み付きやすい布類をこまめに洗濯することもポイントです。
加えて、自分自身が臭いに敏感な状態を保つことも忘れてはなりません。
結局のところ、その空間の〝気〟を決めるのは、そこにいる〝人〟だからです。
私たちは「鼻うがい」(人肌くらいに温めた生理食塩水を鼻から口に通す浄化法)を習慣化しています。
これにより鼻腔をキレイにしておくと嗅覚が正常に保たれ、気に敏感でいられるのです。
芳醇(ほうじゅん)なお茶を淹れるにも、馥郁(ふくいく)たる空間を演出するにも、自分自身の放つ〝気〟が決め手になります。
いつも清々しい気持ちで生きるには、明確なゴールをもって、思い残すことのない毎日を送ること。
どんな運命が訪れようと、そのゴールへ突き進むと、腹を決めて生きている人は、おのずと芳香も味方にできるのです。














